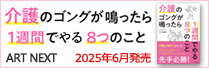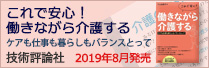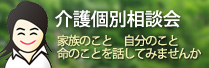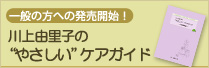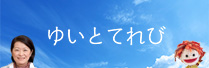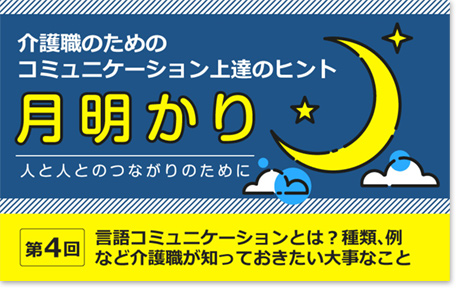「ゆうゆう8月号」(主婦の友社発行/7月1日発売) にて、「私の介護体験」をご紹介いただきました。
これまでも「ゆうゆう」では読者のご相談に答え、専門家としてアドバイスという機会をいただいてきましたが、今回は初となる私自身の介護について。
ちょうど昨年の夏、主婦の友社からいただいたゆうゆうの最終原稿を確認をしている頃、私は家族の急変対応で病院や実家を走り回っていました。
その後、書き下ろした結人ブログがゆうゆうご担当者の目に留まり、今回の取材依頼をいただくきっかけとなったのです。
自分や家族の状況を公開するのは実はとても勇気がいること、神経を使うことですが、亡き父に寄り添った介護のある暮らし、健康だった母の医療発生から治療、在宅介護の準備、働きながらの行動や気持ち、関わり方のコツなど、家族の驚きや工夫を感じてくだされば幸いです。
全国の書店、主婦の友社公式HP,アマゾンなどで購入が可能です。
他の方々の介護体験もとても参考になります。
ご興味ご関心のある方はこちらからご覧ください。
記事内でも紹介していますが、昨年11月から週に1回、朝9時からの45分は母と理学療法士のリハビリタイム。
入院前のように自立した生活ができるようトレーニングに励む母。
この写真はリハビリ開始4ヶ月後、理学療法士Uさんが、「娘さんに送りましょう」と撮影してくれたそうです。どちらもかっこいいですね。^^
母の頑張りとパワーアップが離れている私にも伝わり拍手喝采。
粋な理学療法士さんです。
東京で忙しく働いている私も「今日はどうだった?」毎回訪問者と母との会話や出来事を電話で聴くことが楽しみです。
介護保険には様々な課題がありますが、担当ケアマネジャー、訪問看護師、理学療法士、地域ボランティア、民生委員など、母を支援するチームがいることで、母にも私たち家族にも安心感が生まれました。
母は要支援2、専門職の力に支えられながら心も体も少しずつ回復しています。
要支援の状態は介護状態になることを予防できるか否か、とても大切なステージです。
7月19日は要介護認定の更新のため2度目の訪問調査。
一年前の苦しみを思い出してきっと母も緊張感を感じていることと思います。
きっと大丈夫、乗り越えましょう。
みなさんにお伝えしたいこと。
今回の掲載記事では深掘りしていませんが、緊急時の対応、救急車を呼んだ時の質問に、即答できることでその後の対応が迅速に運びます。
プロの私でもやはり身内の意識消失にはかなり動揺しました。
でも、日頃のコミュニケーションが生きた瞬間です。
対象者の今の呼吸や意識など状態、救急車を呼ぶことになった経緯など落ち着いた口調で次々と質問が投げかけられます。
親の住所、連絡先、かかりつけ医療機関、内服薬、既往歴、現病歴、血液型などは必ず答えられるよう記録保管しておきましょう。
もしご両親がスマートホンをご利用ならば、iPhoneでは「メディカルID」、Androidでは「緊急情報サービス」に上記の情報や緊急連絡先を登録しておくことで、万が一外で一人で倒れて意識がない時などに、スマホがロックされた状態からでも救急隊員が内容を確認することができます。
ご両親に情報を確認しながら登録しておくことをお勧めします。
→【参考リンク】「スマホの設定が命の危険を救ってくれることも? “実はそんなに手間じゃない”緊急情報の登録方法【iPhoneもAndroidも】」(文春オンライン)
そして、瞬間的な衝動で大きな決定をせず、仕事を続けながら支える道を探しましょう。
詳細は本誌をご覧ください。
ゆうゆうご担当者様、書く力をお持ちのライター様、これまでにお読みいただき心からの感想をお寄せいただいた皆様、そして協力してくれた母、ありがとうございました。
まもなく梅雨も明け、蓮の開花も楽しみな季節です。
激しい雨や落雷に注意しながらも夏の始まりをお楽しみください。
共に頑張りましょう。