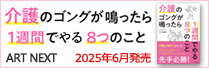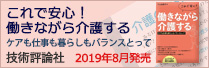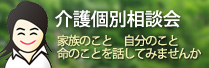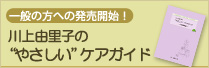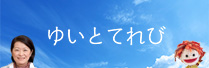「仕事と介護の両立」研修に行ってきました。
冬から春にかけて、「仕事と介護の両立支援」のための研修が続きました。
先日、通い慣れた街に足を運びました。
都心の街にも春の空気が流れています。
70分の時間をいただきました。
介護は生活の一部。お困りごとは介護のみならず、住まい、お金、権利擁護、家族関係、仕事など多岐に渡り複合的です。
特に介護にお金がかかることをご存知ない方が多く、突然の混乱を招かないためにも、介護の実態、正しい情報、今からできることを伝えます。
介護費用負担を軽減する制度は、ご存知なければ利用することができない制度もあります。忙しい合間に自分で情報を得ることはなかなか難しいですね。
日頃からアンテナを張っておくこと、相談場所を知り備えておくことが大切ですが、地域の相談機関、「地域包括支援センター」の存在をご存知ない方もまだまだいらっしゃいます。
また、福祉や医療の専門職が対応する地域包括支援センターのみでは解決できない問題も多々あります。
公益財団法人生命保険文化センターの令和3年全国実態調査では、介護にかかる費用、初期費用74万円、月額83,000円、介護期間は5年1ヶ月です。皆さんどう思われますか?
勿論介護は100人100通り、個人差がありますが、介護保険(1割〜3割)対象の費用のみでは賄えないという意識は持っていたほうが良いですね。
私のご相談に多い介護保険外サービスは、保険外の家事支援サービス、見守りサービス、配食サービス、緊急通報サービス、などです。
最も費用が嵩むのは高齢者施設への入所や住宅改修です。
・運動・食事・趣味など健康を心がけ明るい生活を送る。(介護予防につながる)
・加齢を受け入れながらペースを落としてもクオリティは下げず続ける。
(QOLを高める)
・家族、友人や地域とのコミュニケーションを心がけ、助け合える人間関係を心がける。
・困った時に助けてと言える、弱みをみせられる自分作り、関係づくり。
これも大事な備えですね。小さな私の心がけでもあります。
介護費用への備えとしては、公的介護保険の活用をする。
介護保険以外の民間介護保険も検討する。
支える自分が利用できる仕事と介護の両立支援保険に加入する。
働き方を変えながらも働き続ける。
様々な考え方やサービスが生まれています。
残念ながら老後は安心!といえる日本でありませんが、ひとそれぞれの工夫ができる時代でもあります。
研修やセミナーに参加された皆様には、自分ごととして考えるきっかけにつながってくれたらと思います。
帰路は足を伸ばして東京駅側に、てくてくてくてく・・・
新緑が嬉しい丸の内を通り抜け、てくてくてくてく・・・
美術館近くの丸の内のカフェでお昼ごはん。
大きなそば粉のガレット△とコーヒーでひと息です。
毎回反省と課題が満載ですが、貴重な機会をいただいたことに心から感謝です。
ご依頼いただきました皆様、本当にありがとうございました。
人は皆支えたり、支えられたりします。
特に人生の後半は誰かのお世話になる時間が必ず訪れます。
その時間が少しでも悔いのない善き時間となりますように。